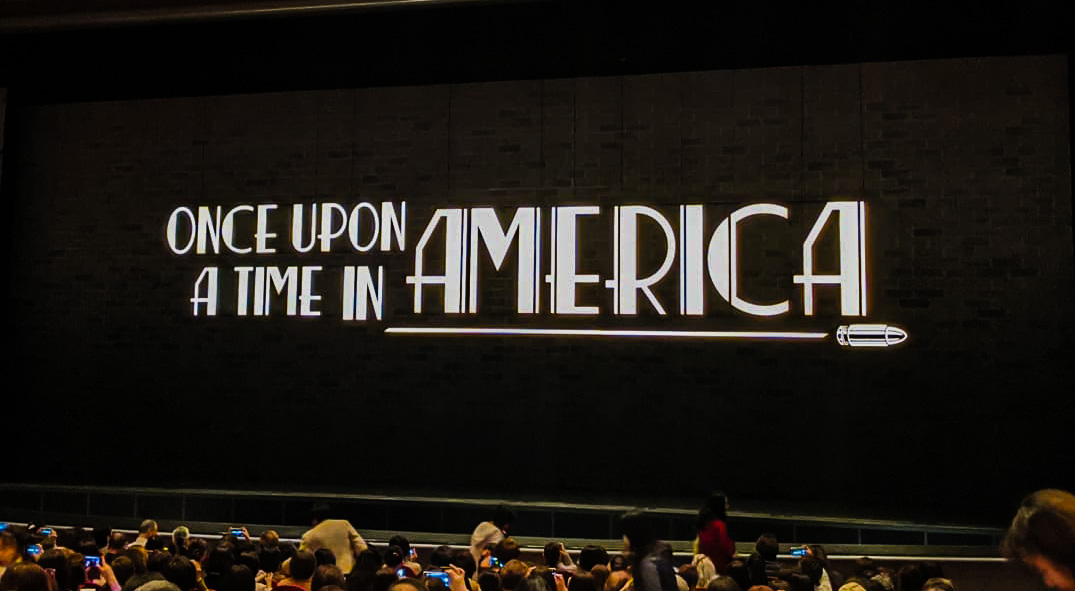雪組の『ONCE UPON A TIME IN AMERICA(ワンス アポン ア タイム イン アメリカ)』を見てきました。その感想。
先日の雪組トップコンビ退団発表で激しく落ち込み、ここ最近はこの公演が、望海風斗・真彩希帆がいかに素晴らしいかをずっと考えていた。ほんと退団しないで・・・
原作映画について
原作は4時間近い大作で、運命に抗い叶わぬ夢を追い求める男たちの、バイオレントで哀愁漂うギャング映画。禁酒法の時代、酒の密売でギャングが幅を利かせていたアメリカ、マンハッタンに生きるユダヤ人、ヌードルスの少年期~壮年期が描かれる。
主人公ヌードルスは寡黙な切れ者で、貧しい生まれだが大きな夢を抱く野心家。ただ、心から欲しいものに手を伸ばしても拒まれたら手を引っ込めてしまうような繊細さがある。
原作映画で描かれるヌードルスは全く「舞台向き」なキャラクターではないのだ。ストーリーを動かすのは他のキャラだし、演じるデニーロは嬉しくても悲しくても眉を少し動かすくらい。4時間かけて具体的な結論は出ず、心に残るのは人生の悲哀。
ヌードルスがペラペラ喋って歌って、感情丸出しにしたらそれ、別人じゃない? 暴力描写も頻出で、すみれコード(宝塚的規範)的にアウトでしょ・・・。
と思ってたら、見てみたら大傑作だった。全部褒め始めたらきりがないから、主演のトップ二人、脚本・演出の小池先生の天才っぷりについて挙げていく。
主演二人(望海風斗・真彩希帆)の歌声の説得力
ヌードルスを演じる望海風斗様(のぞ様)は、歌唱力の高さは言わずもがな歌声が太く中低音がとても魅力的 (しかも音域も広い)。男役の歌は基本、キーが低い。どうしても女性は歌声となると高くなりがちで、無理に低くすると音量が出なかったり、ピッチが不安定になることもある。その点、のぞ様の歌声は全くその心配がない。ヌードルスの男の哀愁を、完璧に歌で表現してらっしゃった。
「上手に歌える」なんて次元の話ではなく、役を歌声で表現できてしまう人なのだ。感情をそのまま歌にのせ、心に訴えかける。ステージで全世界の輝きを身にまとい体全体で歌ってらっしゃるお姿・・・泣ける。退団しないで。
そして男達のミューズであり妖精的な魅力を放つヌードルスの想い人デボラを、美しく伸びやかな歌声で表現できるのも真彩希帆しかいない!! 彼女も、感情をそのまま歌にできる人だ。
かなりの高音を出しても、キンキン痛くなく音質が丸い。場面によって儚く、力強く、歌声のニュアンスを完全にコントロールしてしまう真彩希帆様、大変素晴らしいです。大好き。退団しないで。
(CS番組で、「キーが高い歌は念の為3度上を歌ってからステージに出ていく」と言っていた。ハイレベル過ぎてクラクラする)
宝塚の娘役は一歩引いて男役を立てる「お作法」があるけど、いい意味で希帆ちゃんはのぞ様と並び立ち、相手を最大限尊重しながら、自分の表現したいものもしっかり持った娘役さんに見える。 そんなところも好きだよ・・・
「歌」で役を、感情を、人生を表現できるトップ二人。こんなコンビ、もう出会えないんじゃないか・・・
望海風斗様の重たい芝居
「地味」と言われることもあるけど、のぞ様は基本一つ一つの芝居が重たい(そんなところも大好きです)。ヌードルスというキャラクターを舞台で演じる上で、これも大きなメリット。
ヌードルスは基本渋い男なので、いくら舞台化だとしても元気に歌って踊るのは違う。となると、やはりどっしりした芝居や力強い歌声で「重ねた年月」や「秘めた感情」を表現することになる。そういう芝居は、若手やキラキラ系スターにはできないものだ。
ヌードルスという役は、奇跡のようにのぞ様にぴったり。この時点でもう大傑作は約束されたようなもの。
象徴的なアイテム
もともと映画でも「コインロッカーの鍵」が重要なアイテムとして出てくるが、舞台ではさらに象徴的なアイテム・人物が付け足され、強調されている。「革ジャンを着た若者たち」「ダビデの星」「赤いバラ」「スピークイージーの歌姫」など。
カット割りで物語を演出できる映画とは違い、舞台上ではたくさんの人物がそれぞれの演技をしていて、生身の人間が動き、踊り、歌うのだ。観客側はスクリーンを見ているときより多くの情報を一瞬で受け取っているので、大袈裟に言うと「大きく・華やかで・特徴的なもの」なものしか覚えていられない。
だからストーリーを整理し、キャラクターを明確にし、キーとなるアイテムを強調する必要がある。その点で今回の舞台化は大大大成功だし、その賢いやり口に感動した。
整理されたストーリー
映画はヌードルスの回想のような形で描かれるため、ストーリーの時系列がバラバラで、一部不明瞭なエピソードがある。
その不明瞭さと、過剰なバイオレンス、女性視点の欠如等が宝塚的に正しい形(と思われるもの)に賢く整理されていることに驚いた(それは同時に、映画独自の味わいも削ぎ落とすことにもなるのだけど)。
たとえば映画では現実味のない、妖精のように描かれる若い頃のデボラも、舞台では一人の夢を追う女性としてしっかりと人物像が作られている。(映画版はヌードルスから見たデボラなのでまさしく理想の女、天使のよう)
ここでいい役割を果たすのが、舞台オリジナルキャラのデボラの幼なじみニック(綾凰華)。綾凰華は真彩希帆と同期でもあり、「夢を一緒に目指す仲間」というキャラ設定が、実際のふたりの関係性を思わせるのが大変素晴らしい。いかにも「宝塚的」なサービスだし、デボラというキャラクターに温かい人間味をもたらしている。
小池先生は原作映画が昔から好きだったと言っていた。好きな作品をアレンジする時に、こんなにも「エゴ」を出さず、まっすぐ観客の方に向けるものなんだと、そこも感激した。迷いのない、バランスの取れた、鮮やかな改変。
舞台ならではのお楽しみ
デボラがマンハッタンの劇場で歌うシーン(舞台オリジナル)。キラッキラの巨大なステージ衣装(もはや舞台装置)と大勢の踊り子を伴って登場するのだけど、これが生で見るととんでもない迫力。このような「舞台の醍醐味」が堪能できるシーンをきちんと用意してくれているのも嬉しいところ。
「醍醐味」でいうと、ヌードルスが阿片窟でトリップして幻想を見るシーン。これが最高に芸術的で恐ろしい!
幻想のシーンは「ファントム」や「エリザベート」など名作舞台でも出てくるけど、大勢の生身の人間が演じる幻想は圧倒的なリアリティがあり、映像では決して得られない、身に迫るような恐ろしさがある。
さらに舞台セットの切り替えも鮮やかで、気がつくと背景が変わっていたり、セットの切り替え自体に演出上の意図をもたせているシーンもある。あまりにもなめらかで自然なので気が付かないくらいだ。セットを観察するためだけにもう一回見たい。
映画を舞台化すること
最近映画「CATS」を見て絶望したので、「舞台と映画」について考えることが多かったが、今回の「ワンス」は間違いなく大成功だったと思う。やはり、明確な意図を持った「改変」は必要なのだ・・・
原作を見ている人とってにも宝塚なりの「別解釈」として楽しめるし、舞台しか見ないひとにも見どころが沢山あるし、宝塚を初めて見るひとにだって楽しい舞台のはずだ。
見たあとにこんな分量の文章を書いてしまうほど作り込みの細かさを感じた素晴らしい作品だった。Blu-ray買ってあと1000回は見ると思う。キャスト一人ひとりを褒め始めたら1万字を超えそう。